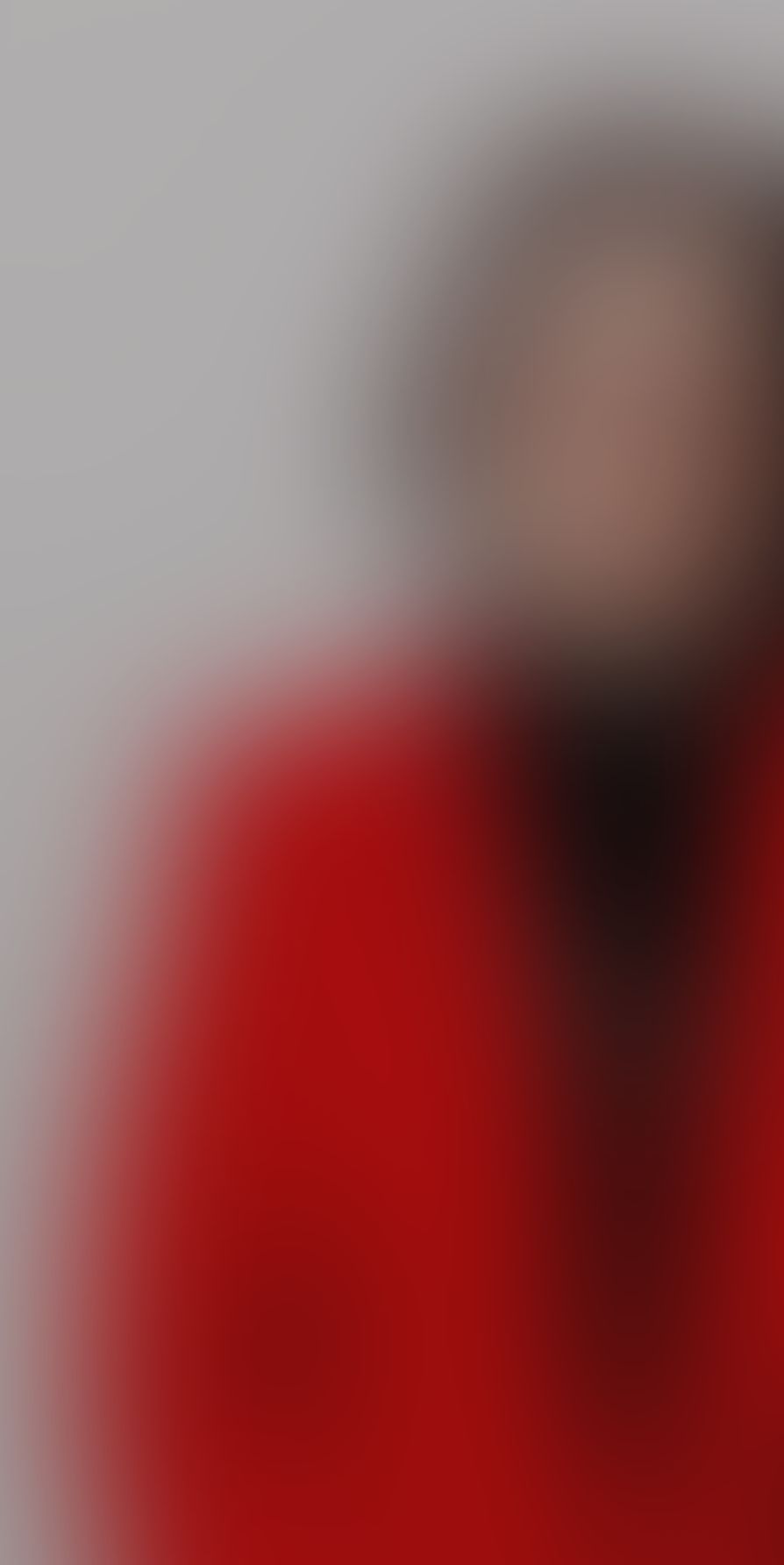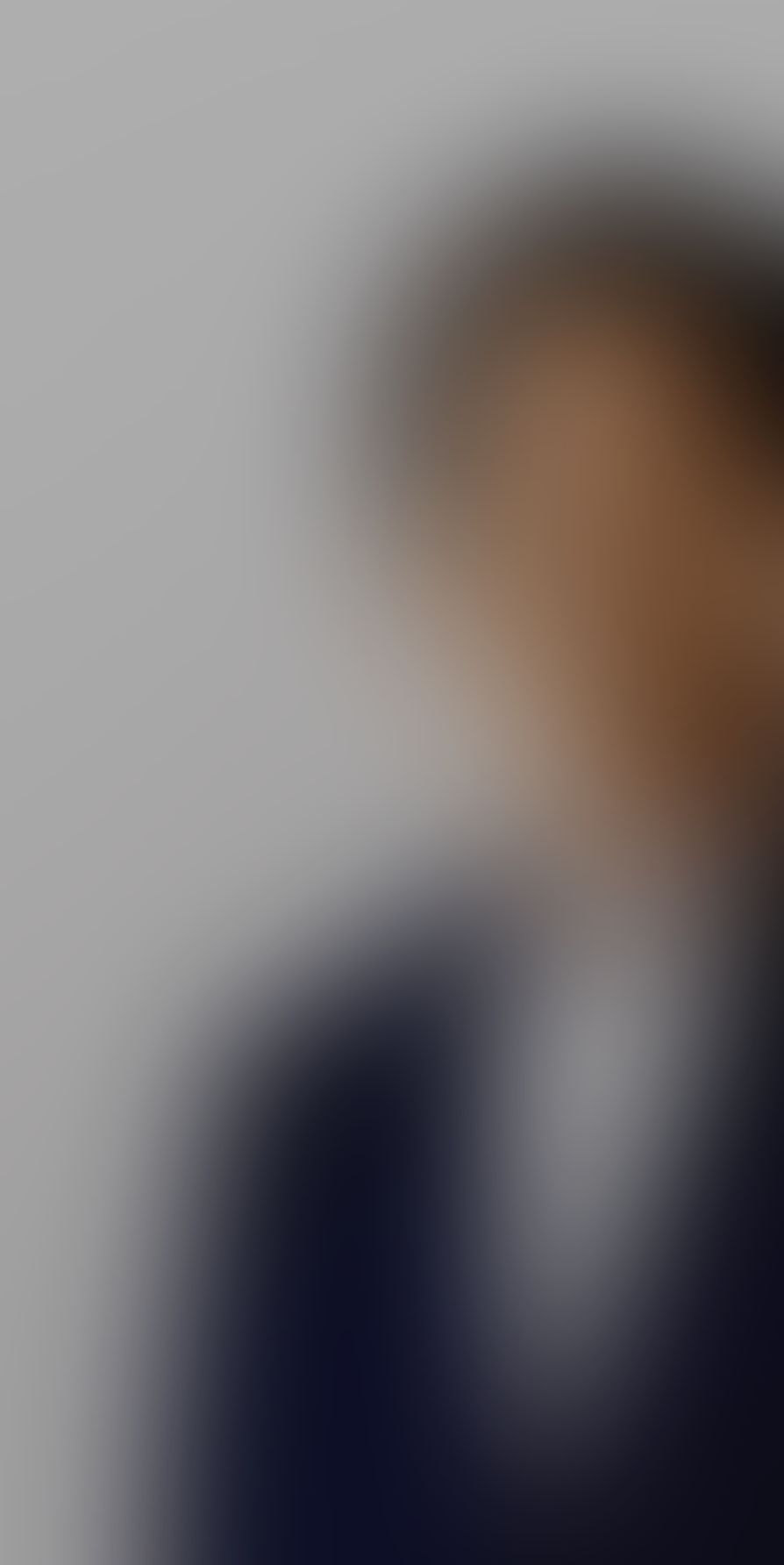国際共生学部 国際共生学科
COLLEGE OF GLOBAL ENGAGEMENT
School of Global Engagement
Engage with the world through our innovative program to make positive contributions to global society.

全科目を英語で学び、Experiential Learningをコンセプトに実践的な学修を展開し、世界を舞台に活躍する実力を養います。授業を通して修得したコミュニケーション力や知識を駆使し、さまざまな国・地域の人たちとプロジェクトを実践することで、学びの深さと幅を拡大。大学の講義で学んだ知識の定着はもちろん、主体的に行動する姿勢や社会で役立つ実践的スキルの修得、さらに本質的な視点から社会課題を見つけ、改善策を探求する力を身に付けていきます。

英語力と国際共生に不可欠な知識・スキルを集中的に修得
English for Global Citizens(EGC)は、Content-based Approachの学修法を用いたアカデミックイングリッシュ修得プログラムです。多様な文化的背景や価値観を持つ人たちと協働するための高度な英語力やコミュニケーション力、マインドを養成します。また、デジタル化が進むグローバル社会で必要なデジタルスキルの基礎や情報技術の活用法についても学び、グローバル市民としての実践力を磨きます。
【取り扱うテーマ】グローバルな諸問題
人権、難民、平和維持、貧困・飢餓 、世界遺産、ビッグデータ など
SDGsを始めグローバルな課題に焦点を当て、学生はディスカッションやプロジェクトベースの学修を通じて批判的思考力と実践的なスキルを養成。国際社会で活躍するためのグローバルな視野を養います。

グローバル社会の課題にアプローチするため
3つの学問分野を幅広く学ぶ
1年次のEGCで培ったアカデミックイングリッシュを土台とし、2年次から英語で人文科学(Humanities)、社会科学(Social Sciences)、ビジネス・経済学(Business & Economics)の3つの分野から幅広く履修し、多角的な視点でグローバル社会の課題にアプローチします。留学生とともに学びプロジェクトに取り組みながらさまざまな価値観に触れ、グローバル市民としての姿勢やマインドを養います。
【科目例】
- Humanities
- History of Asia/Intercultural Communication/Religion and Philosophy など
- Social Sciences
- Survey in Sociology/Global Diplomacy and Asia/Sustainable Development など
- Business & Economics
- Global Economics/International Business/Global Leadership など

グローバルチャレンジ留学で実践力を磨く
英語力やコミュニケーション力、学修分野での基礎知識を身に付けた後、希望者は1年間のグローバルチャレンジ留学で実践しながら学修します。留学先大学(学士課程)の授業を英語で履修するとともに、学生自身で設定したグローバル社会の課題解決に向けて取り組みます。
【取り組み例】
-
アメリカの大学で授業を履修
Intercultural Conflict/
American History など課外活動で移民児童の
学習支援ボランティアに取り組む -
オランダの大学で授業を履修
Business & Society/
Digital Marketing など現地の日系企業で
就業体験に取り組む

Experiential Learning 実践力を磨く体験型学修
国内外での就業体験、留学先大学が提供するサービス・ラーニングなど体験的な学びの機会も豊富に展開しています。さまざまな活動を通し、授業で学んだことを活用しながら高度な実践力を身に付けます。
- 【主なプログラム(予定)】
- Service Learning / Community-Based Learning / Project Engagement / Internships / Talent Development / Leadership Program など
Academic Calendar
1年次秋学期以降は、海外の学年暦に準じて授業を行います。