NEWS ニュース
関西外大国際文化研究所の連続講座「流転の冒険者たち:アフリカの妖術と現代」がスタートしました。次回は12月13日(金)です
関西外国語大学国際文化研究所(所長・竹沢泰子教授)が主催する連続公開講座「流転の冒険者たち:アフリカの妖術と現代」が12月6日、中宮キャンパスで始まりました。文化(社会)人類学が専門で、アフリカ現代社会論などを研究している近藤英俊・外国語学部教授が講師を務め、3回にわたってアフリカ大陸の国々で見られる妖術と現代社会とのつながりを詳しく解説します。
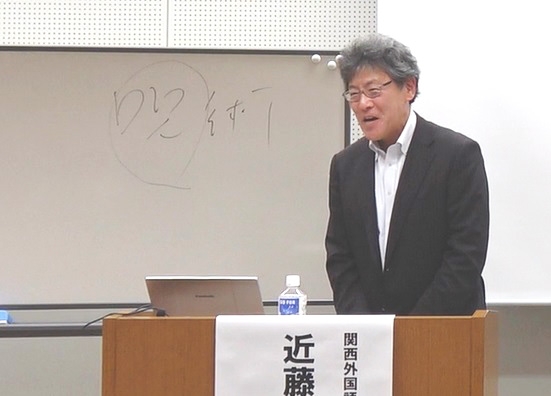
▲呪術の概念について解説する近藤教授
初回は「暴走する妖術」がテーマです。近藤教授は、呪術や妖術がアフリカに特有のものではなく、日本でも病気平癒を願う「お百度参り」などの風習に見られるように、世界のどこでも意外に身近なものだと説明、そのうえで、南アフリカ、コンゴ、ガーナの3カ国の妖術と現代社会について、話を進めました。

▲地図を指しながら解説をする近藤教授
南アフリカでは1990年に起きた、妖術使い(ウィッチ)にされた老女が若者から暴行を受けて死亡した事件を取り上げ、老女を襲った若者たちが「お前ら妖術使いのせいで、仕事がない」と言っていたと紹介。コンゴでは、内戦やエボラ出血熱などの感染症の蔓延でストリートチルドレンが増加し、こうした子どもたちの多くは妖術使いとみなされて家を追い出された、と背景を説明しました。ガーナには、妖術使いとされた成人女性が集団で自活しながら暮らす「ウィッチキャンプ」が複数あり、キャンプは、暴力にさらされた女性の逃げ場にもなっている側面もあるとしました。
近藤教授は、南アフリカの学者ジーン・コマロフ、ジョン・コマロフ夫妻の研究をとり上げながら、「アフリカの都市では、スマホを見ながらファストフードをほおばる若者がいて、一見、先進国の風景と変わらない。しかし、社会的な格差は大きく、自分が成功できないのは呪術や妖術のため、と考える人々もいる」と社会的な背景を解説。「ただ、格差だけでは説明しきれない問題もあり、次回以降に掘り下げたい」と結びました。
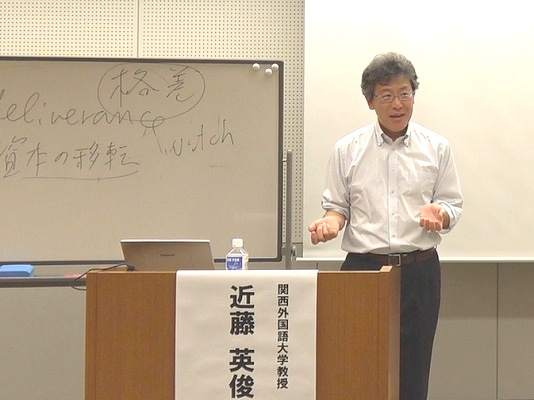
▲社会的な格差と呪術の関連性について話す近藤教授
会場には、学生や教員だけでなく、一般の参加者もおり、「未知の社会の話で、興味深くお話を聞きました。次回も楽しみにしています」などの声が聞かれました。
次回以降の日程とテーマは以下の通りです。
▽12月13日(金) 「偶然と必然を結ぶ妖術」
▽12月20日(金) 「渦中の人々:都市化と妖術」
.jpg)
▲次回は12月13日です
いずれも午後3時からで、参加無料、予約不要です。参加ご希望の方は、直接会場の中宮キャンパス5号館にお越しください。
