NEWS ニュース
≪研究室から≫ 長谷川通教授(国際共生学部)/国際機関を志す人は専門性と文書作成能力を高めよう
はせがわ・とおる/1991年東京大学経済学部卒業。同大学大学院経済学研究科第2種博士課程(応用経済学専攻)前期修了、同博士課程(現代経済専攻)後期修了・博士(経済学)。ノースウエスト航空などを経て、2000~2022年、国際民間航空機関(ICAO)本部(カナダ・モントリオール)で航空運送局エコノミスト、同局長補佐、総務局収益生産管理課長、航空運送局副局長などを歴任。2022年関西外国語大学外国語学部教授、2023年国際共生学部教授。
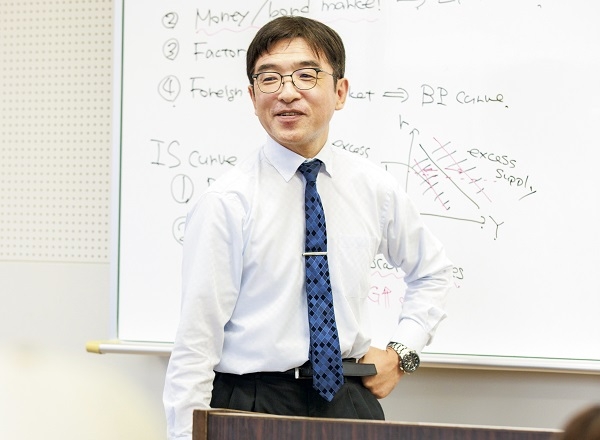
――大学院時代の研究テーマは航空運賃とうかがいました
学生時代、海外旅行サークルに所属し、一人旅を楽しんでいましたが、航空券の高さが悩みの種でした。旅行費の半分近くを占める航空券代を少しでも安く抑えられないかと模索するうちに、旅行そのものよりも航空運賃の仕組みに興味を持つようになりました。
大学院に進学し研究テーマを選ぶ際、「競争と航空運賃の関係」に注目しました。一般的に競争が激しくなれば運賃は値下がりすると思われがちですが、現実には逆に値上がりする運賃もあります。この一見矛盾する現象を解明するために、実証研究に取り組み、経済学の博士号を取得しました。
■カナダのICAO本部に20年余り勤務

▲第三回国連開発資金国際会議全体会合でICAO代表として演説(2015年)
――ICAO本部に勤務されることになった経緯を教えてください
大学院修了後、研究成果を実務に活かしたいと思い、米系航空会社で太平洋路線の価格設定を担当しました。1999年秋、IATA(世界の航空会社が加盟する業界団体)の運賃会議に出席するためモントリオールに出張した際、隣接するICAO(国際民間航空機関)本部を訪れる機会がありました。この訪問がきっかけとなり、翌年、航空運送局のエコノミストとして採用されました。
ICAOは、日本を含む193カ国が加盟する国連の専門機関の一つです。航空輸送に関する国際基準の策定を担っており、パスポートの仕様統一にも関わっています。

▲国際交通フォーラム閣僚セッションでICAO代表として発言(2019年)
――ICAOではどのような業務を担当されたのですか
9年間、経済的規制に関する専門業務に従事した後、局長室へ異動し、予算、人事、経営戦略など管理業務に携わりました。そこで「If you ever need any help, just ask Toru」という評判と信頼を築いたことが、収益生産管理課長への昇進につながりました。当時、ICAOの営利事業は赤字を抱えていたのですが、事業再編を推進し、1年で黒字化に成功しました。
2015年、経済部門を統括する航空運送局副局長に任命され、上級幹部会の一員として組織の中核を担うようになりました。本来の職務に加えて、最高データ責任者や総務局副局長代理を兼任、特命事項も担当したため、複数のパズルを同時に解くような日々が続きました。調整や折衝がルーティンとなる中で、閣僚会議がシナリオ通りに閉幕した瞬間や、パンデミックの航空業界への影響をいち早く予測し公表できた時には、パズルのピースがぴたりとはまる達成感を得ました。
■パワーポイント使わず板書で授業

――担当する授業についてご紹介ください
経済理論系の2科目では、国際共生学部が掲げる「世界が抱える課題解決への貢献」に不可欠なツールを学びます。理論を理解すれば、価値観に影響されず、複雑な問題の本質を捉えられるようになります。
ただし、授業内容を暗記しても、経済理論は身につきません。問題演習による訓練が必要です。そこで、授業時間外に宿題などの個別指導を行っています。
どの授業も、パワーポイントを使わず板書で進めています。「板書量が多すぎる」とよく言われますが、ノートを綺麗にとる必要はありません。論理展開を追いながら記録する、その過程自体に価値があるのです。
――学生のために研究室をオープンにしているそうですね
研究室にいる時間はすべてオフィスアワーです。赴任当初、訪れる学生は限られていましたが、現在では学期中ほぼ毎日、複数の学生が来るようになりました。授業を履修中の学生よりも過去の履修生の方が多く、私と面識のなかった学生もいます。
勉強やキャリアに関する相談と個別指導が約7割で、それ以外にも毎週ランチタイムに顔を見せるグループから、旅行手配の相談、雑談や休憩、自習の場所とする学生まで、目的はさまざまです。
学生との交流を通じて、実は私自身が多くを学んでいます。学生ならではの率直な視点や意見は、私の思考を刺激し柔軟なものにしてくれます。
■組織論理を尊重し、正論以外も受け入れる柔軟さも必要
――国際機関への就職を志望する学生にアドバイスをお願いします
志望者の多くは、「国際貢献」や「グローバルな課題解決」といった理想を抱いています。しかし、国際機関は、厳格な階層構造と専門分化された業務、複雑な意思決定プロセスを持つ官僚組織です。若手や中堅職員に任されるのは、会議資料や報告書の作成など地道な仕事です。したがって、学生時代から専門性と文書作成能力を高めておくと有利に働くでしょう。
日々の業務への真摯な取り組みは、組織内での評価を高め、キャリアアップへとつながります。職位が上がると視界も開けます。
しかし、理想の実現には、マネジメント能力だけでなく、組織論理を尊重し、正論以外も受け入れる柔軟さが必要です。情報、人脈、要領、そして政治的な感覚も欠かせません。こうした技量を身につけ、国際社会をリードする人材へと成長してください。
