NEWS ニュース
国際文化研究所・公開講座「イスラームを知る -インドネシアにおける変容-」を開催しました
関西外国語大学国際文化研究所が主催する連続公開講座「インドネシアのイスラーム世界 –信仰・女性・地方文化 –」。
全3回にわたって開催される同イベントの第1回目の講座「イスラームを知る –インドネシアにおける変容–」が、11月27日(土)中宮キャンパス・マルチメディアホールで行われました。

▲国際文化研究所所長の野村亨教授。
講師を務めたのは、本学教授で国際文化研究所所長を務める野村亨教授。
講座ではイスラーム教全般の解説があった後、「インドネシアのイスラームの特色」について講義が行われました。
「インドネシアではイスラーム教の広がりとともに、神と人間との一体感を求める民衆的な信仰である神秘主義(スーフィズム)が生まれ、12世紀ごろから神秘主義教団が誕生。イスラーム教の各地への拡大の原動力になりました」と野村先生。
聖典であるコーランの知識や規則よりも、感覚で神と一体となるスーフィズムの存在が重視されたのがインドネシアのイスラーム教の特色で、コーランの教えに厳格に従おうとする中近東のイスラーム諸国との大きな違いになっていると解説されました。

▲「ヒンドゥー教、仏教、先祖崇拝、自然崇拝などの要素も多分にまじりあっており、インドネシアのイスラームは比較的自由度が高いのが特色」と野村教授。
その後もインドネシアのイスラーム教の特色が時代の変遷ごとに語られ、最後に「まとめ」として、非イスラーム教徒として配慮するべきことが紹介されました。
具体的には…
■お祈りの時間を配慮する
■左手は使用しない
・不浄の手とされている手を使わないように
・万一使用してしまった時は謝罪の言葉を一言
■断食(プアサ)中、飲食をする場合は周りへの配慮も忘れずに
といった解説がなされました。
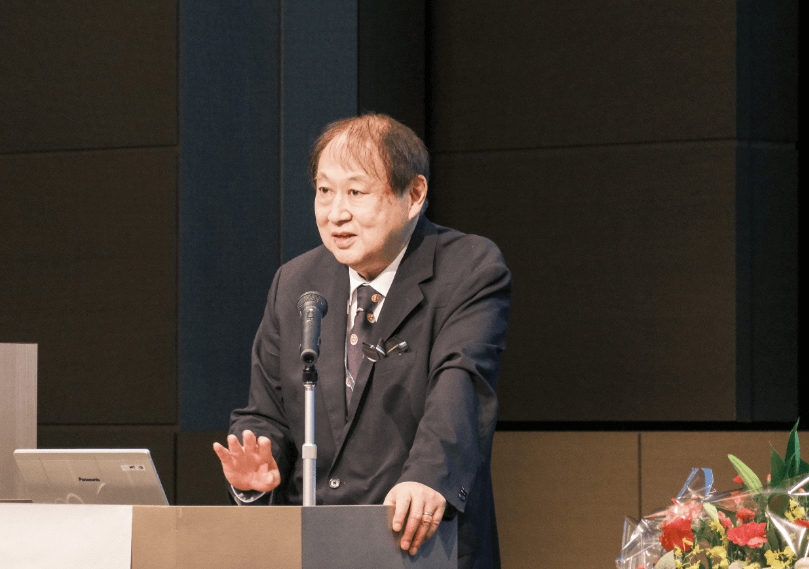
▲「神秘主義(スーフィズム)の行者のことをデルヴィッシュといい、父親がイラン人のダルビッシュ有の苗字の語源になっている」といったこぼれ話も。
なお、野村教授は今年度で本学を退職されます。
最後に「1977年に高校の教壇に立ち、そこから今日に至るまで教師を務めてきました。教師という職業は本当に天職だと思っておりまして、悔いのない人生を送らせていただいたと感謝しています」とご挨拶され、会場から大きな拍手が送られました。
連続講座「イスラームを知る –インドネシアにおける変容–」の次回以降の予定は以下になります。
■第2回:12月4日(土) 17:00~19:00 関西外国語大学 中宮キャンパス・マルチメディアホール
野中 葉 氏(慶応義塾大学准教授)
「ムスリム女性のヴェールと服装 –インドネシアを事例に–」
■第3回:12月11日(土) 17:00~19:00 関西外国語大学 中宮キャンパス・マルチメディアホール
メタ・スカル・プジ・アストゥティ 氏(ハサヌッディン大学教授)【中継】
「インドネシアのイスラーム –日常の実践から–」
各イベントの申し込みは以下のリンクからお願いします。
ふるってご参加ください!
https://www.ocans.jp/kansaigaidai/schedule?fid=R8C6tqGZ
