NEWS ニュース
≪研究室から≫ 牛承彪教授(英語国際学部)/歌謡文化の本質を求めて 中国の少数民族トン族を研究
ぎゅう・しょうひょうNiu chengbiao/中国吉林省延辺朝鮮族自治州出身。吉林大学卒業(日本語・日本文学専攻)。1998年来日し、奈良教育大学で修士号、名古屋大学で博士号取得。専門は文化人類学、文学など。2007年関西外国語大学国際言語学部講師。2016年から英語国際学部教授。日本・中国・韓国における農耕歌謡を総合的に比較する視点から調査・研究。2011年以来、科学研究費補助金(科研費)を受け、中国貴州省のトン族居住地域で調査を実施。櫻井龍彦氏との共著『トン族の歌と饗宴―ポリフォニーの歌声が結ぶ人びとの文化誌―』(2023年、明石書店)で第41回日本歌謡学会志田延義賞受賞。日本歌謡学会会員。
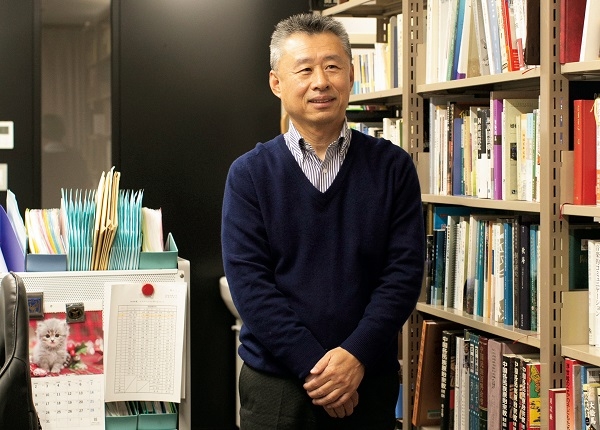
■日本の歌垣と同じ文化
――「歌謡文化」を研究されています。興味をもったきっかけは何でしょうか。
大学院修士課程のとき、指導教員の真鍋昌弘先生(関西外国語大学名誉教授)の影響を受け、歌謡を研究テーマに決めました。特に、中国貴州省などに居住する少数民族・トン族の歌謡を研究対象としています。
博士課程に進んだ2000年代初め、現地でトン族の歌謡に関する実態調査を行いましたが、トン族の中に古い歌謡が残っていることを知り、驚きました。トン族にとって、歌は誰でも歌うものであり、生活の一部になっていたのです。
トン族には、日本古代にあった「歌垣」(うたがき)と同じ文化が存在しています。これらはルーツを同じくし、日本に稲作をもたらした長江下流域の人々と何らかの関係があり、文化面で比較研究する価値があると思うようになりました。
トン族の歌謡文化は、日本古代の歌謡文化の全体像を見るための格好の材料になると確信しました。しかし、歌の多くが消滅しつつあり、歌の伝承者も高齢化するなど継承が課題となっています。

▲国際アジア民俗学会に参加した牛教授(中央)
■現地で計14回の実地調査
――トン族研究は関西外大在職中に加速しました。
大学院の時に受けた感銘と、歌が消滅することへの危機感が原動力になりました。幸い、科学研究費の助成を2011年から2024年までの間に3回にわたり受けることができました。この間、貴州省のトン族地域で実地調査を計14回行い、日本国内でも奄美大島で3回、広島県で2回の調査を実施しました。
これまでに研究代表者として3本の報告書をまとめました。現在、4本目の報告書「中国トン族の儀礼における歌掛けと生活文化」を編集中で、2025年3月に完成する予定です。

▲中国貴州省のトン族地域で調査する牛教授(右)
■日本歌謡学会志田延義賞を受賞
――成果の一つが『トン族の歌と饗宴』(2023年、明石書店)ですね。
名古屋大学大学院時代の恩師、櫻井龍彦先生との共著で、600ページ余りになりました。副題〈ポリフォニーの歌声が結ぶ人びとの文化誌〉は、高音部と低音部が積み重なるようにうたうポリフォニー(多声部合唱)に優れ、旧正月などに、集落間で訪問し合い飲食でもてなす風習があるトン族の特徴を表しています。
この本では、歌と饗宴というカテゴリーを通して、トン族における歌のもつ文化的意義や社会的機能を明らかにし、その社会機構に内在する基本的な仕組みと原理をとらえ、日本の歌掛けとの比較を通して、歌謡の本質を究明を試みました。異性同士で歌を掛け合う文化は東アジアにしか見られないもので、歌謡の本質を把握するための鍵になるのではないかと思います。
本書は2023年の第41回日本歌謡学会志田延義賞を受賞しました。

▲志田延義賞の受賞作を手にする牛教授
――歌とは何か。どのようにとらえていますか。
トン族の事例から、歌は神に向かって歌う、人間同士で絆を強めるために歌う、結婚相手を獲得するために歌う、けがれを払うために歌う、酒を勧めるために歌う、また、(人が脱魂状態になって)霊魂が歌うことがわかります。歌は相手の心をとらえる、相手の魂に働きかけるという手段になっていることは間違いないと思います。歌は、言語とは異なる、特殊なコミュニケーションの手段であるといえるでしょう。
歌謡は当然、現代でも生きています。歌を聴くときも、歌を歌うときも心が動かされることは誰でも感じると思います。歌には昔の田植え歌のような実用的な働きはなくなりましたが、精神状態を安定させる役割は生きています。
――中国吉林省の延辺朝鮮族自治州のご出身です。
吉林省全域にはさまざまな民族が暮らしており、北朝鮮と国境を接する延辺朝鮮族自治州は朝鮮族が集中して居住しています。言語や文化の違いは小さい頃から経験し、異なる民族の文化を尊重し、互いを理解しようとする意識を自然と持つようになりました。母語のほかに朝鮮語を修得し、韓国での調査研究や交流の助けとなっています。日本語は高校時代から学び、大学でも日本語学科に進みましたので、日本での研究に役立っています。

▲中国吉林省の州都・延吉市
■学生に考える力つけさせたい
――4月にスタートする英語国際学部アジア共創学科で授業を担当されます。
アジア共創学科では「ジャパノロジー」「アジアの現代文化」「アジア共創基礎演習」などの授業を担当します。これまでの蓄積や実地調査で得た資料を活用し、知識を教えるとともに、学生が、考える力、課題を解決する力を修得できるよう努めたいと思います。
新学科は新たな時代を見据え、科目、授業内容とも充実しています。学生のみなさんが、視野を広げ、実用的な能力を身に付けるために積極的に授業や実践に取り組み、将来、アジアを舞台に活躍する人材へと成長することを願っています。
