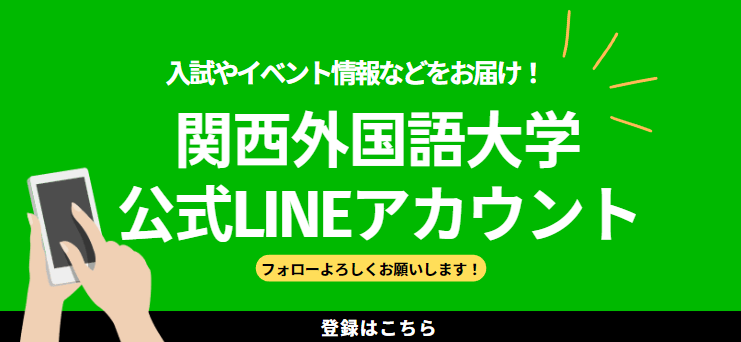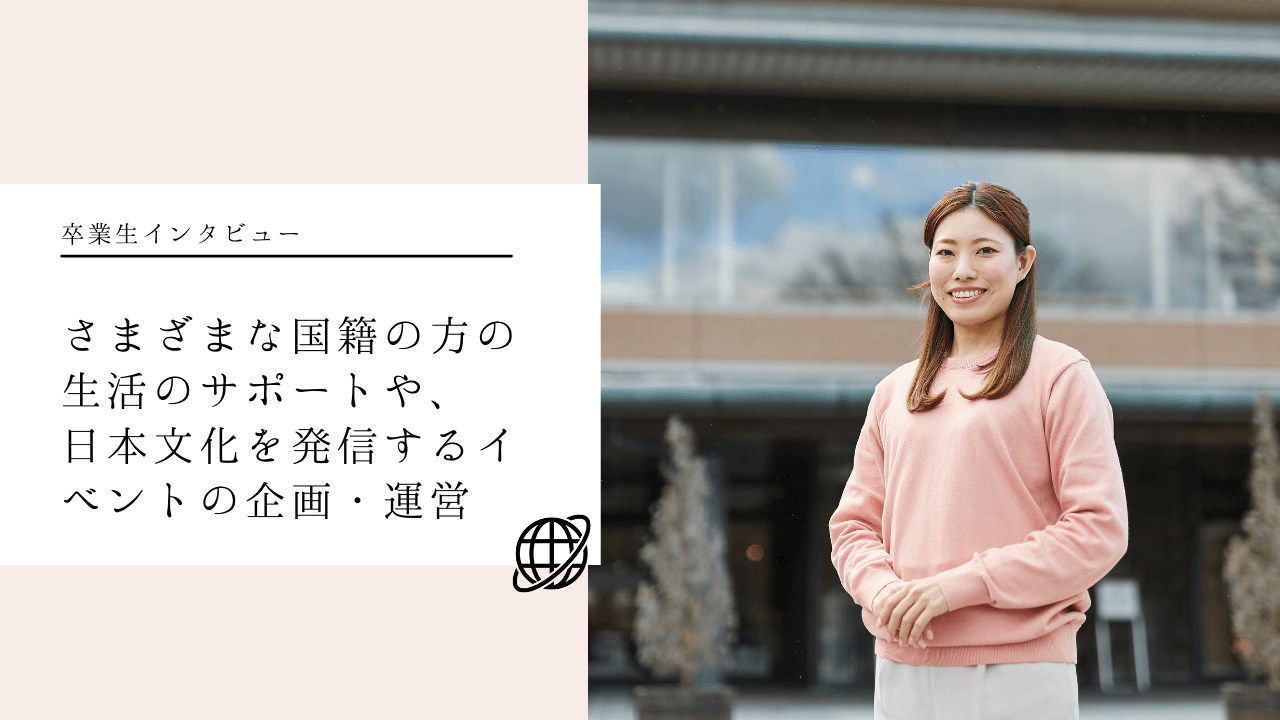「英語×日本語×文化・社会」の学びを実践する外国語学部 国際日本学科が2024年4月に開設されます(設置構想中)。
同学科では、増加する国内企業の外国人材やその家族たちとの共生を支える人材、
さらには日本の文化を海外に発信する担い手が不足しており、その橋渡しとなる「英語・日本語の優れた運用能力を備え、広く文化・社会に精通したグローバル人材」の育成をめざします。
国際日本学科での学びはこれからになりますが、関西外大の卒業生には、グローバル人材として「世界と日本をつなぐ」仕事に従事している先輩たちが数多くいます。
この記事では、そんな卒業生の一人である、京都市国際交流協会で働く山本弥生さんのインタビューをお届けします。
卒業生プロフィール

卒業生プロフィール
- 山本 弥生さん
- 外国語学部 スペイン語学科 2011年3月卒業
- 【勤務先】公益財団法人 京都市国際交流協会

同協会の総務課に勤務し、現在は主に広報関連の仕事を手がけています。
京都市国際交流協会でのお仕事内容について

現在、京都市国際交流協会で働く山本さん。
同施設では、京都市内に住むさまざまな国籍の方の生活のサポートや、日本文化を発信するイベントの企画・運営などを主に手がける。
山本さんがこれまでにどのような仕事を手がけてきたのか、まずはお話を伺った。
日本に来た外国人留学生をサポート

入職当初は事業課に所属し、京都に来ている外国人留学生のサポートを手がけた。
来日した留学生が、京都で生活をスタートさせる際に必要となる支援や交流に関する業務を主に担当し、行政や大学、日本語学校と連携し、留学生を対象としたガイダンスの企画・運営を行った。
その後は各学校での対応となるが、受け入れのノウハウが確立されていない大学だと、
- 市役所
- 郵便局
といった公的機関などの手続きのサポートの仕方がわからないという問い合わせが少なからずあり、それだったら「留学生受け入れ担当の学校職員の方に集まっていただいて、相談会をやりませんか」と山本さんが提案する。

その企画が2019年からスタートし、会合の開催とその後京都市といっしょに留学生受け入れに関するリーフレットを作成しました。
私は異動となって担当を離れましたが、好評を得て、この活動は今も続いています。
そのほか、在住外国人を対象とした
- 日本語クラス
- 地域の小学校を訪問する国際理解プログラム
- 日本人学生との交流イベント
- 留学生と地域の方々との交流イベント(留学生交流ファミリー)
- 隠れた京都の魅力を案内するツアーイベント
などの交流事業や11のボランティア活動を手がけ、一人ひとりが地域の国際化を進めるリーダーとなり活動を広げられるよう、機会の提供や人材育成に対するサポートを行っている。

山本さんが担当したボランティア活動が「留学生交流ファミリー」で、プログラムの概要は以下の通り。
- 年に2回(春・秋)留学生を募集
- 留学生の好きなことや希望、住んでいる場所などを参考にファミリーを決定
- マッチング会(留学生・ファミリーを紹介する会)でファミリーに会う
- 留学生とファミリーが連絡を取り合って交流
プログラムでの交流期間は6ヵ月で、マッチング後の交流は自由となり、季節の行事や京都での日常生活をいっしょに楽しみながら、日本で生活する上での相談相手として精神的な支えとなるなど、日々の暮らしの中で相互の理解と交流を目的としている(※ホームステイプログラムではない)。
山本さん自身、関西外大在学中に留学し、ホームステイを体験しているほか、ご実家が留学生を受け入れるホストファミリーをしていたこともあり、双方の気持ちがよくわかることが、マッチング作業のときにも役立ったという。

参加した留学生から、「日本のお母さんに出会わせてもらえた!」と声をかけられたこともあり、そのときは本当にうれしかったですね。
総務課の業務とともに、広報の仕事を担当

現在は総務課に所属し、京都市国際交流会館のインターン生の受け入れ対応や貸会議室の対応といった総務関連の作業を手がけるとともに、主に広報の仕事を請け負っている
具体的には、
- ホームページの管理
- SNSの統括&情報発信
- 広報誌をはじめとする各種広報物の制作
- メルマガの作成(月1)
- マスコミ対応
- プレスリリースの作成 etc.
などの業務を担当する。

「国際交流」を担う機関だけに世界情勢が仕事に関わってくることが少なくなく、例えば2023年2月のトルコ・シリア国境で起きた大地震の際には、緊急募金設置の広報資料やプレスリリースを急きょ作成。
取材の申し入れがあったテレビ局や新聞社へのコメントの対応も山本さんが担当した。
同様に、ロシアのウクライナ侵攻があった際には、京都市とキーウ(ウクライナの首都)が姉妹都市ということもあり、マスコミ各社からの問い合わせが多数あったほか、避難されるウクライナ人の京都市での受け入れ対応などにも携わった。

ウクライナから避難された方の受け入れ支援としては、以下のような活動に取り組んだ。
- ロシアによるウクライナ侵攻開始から1ヶ月以内に、京都市、協力・アドバイザー団体と共にネットワーク組織を発足
- 京都市国際交流協会が窓口となり、企業・団体・市民の方々と連携
- 具体的な活動として、住居やサービスの提供や募金などを実施

現在、約80人のウクライナの方が京都で生活され、避難者同士の交流会や在住ウクライナ人が企画・運営を行うイベントも実施し、市民からも多くの関心が寄せられています。
さまざまな国の方に配慮し、寄り添った情報発信を心がける

広報活動をする際に心がけているのは、情報発信に偏りがないようにすること。
京都市には世界各国の在留外国人が生活し、多様な理由で来られているので、一部の地域だけに肩入れをするといったことがないよう、多彩な国や文化を対象とした企画が行われている。

情報発信においても、さまざまな立場や状況におかれている人に寄り添うことを心がけています。

業務中に使うのは基本的には日本語となるが、時には英語やスペイン語しか喋れない方から協会に電話がかかってくることも。
そうした際は、山本さんにつながれることが多いそうで、特にスペイン語は山本さんの担当となっている。

外国語学部スペイン語学科出身ですので、そのスキルが職場でも生かされています(笑)。
婚活イベントや子育て支援などの交流イベントも

京都市国際交流協会では、外国人留学生を対象とした「日本語クラス」をはじめ、
- 習字
- 生け花
- 日本舞踊
- 茶道
- 折り紙
などの講座を開講。
そのほか、外国籍市民の子育て支援にも力を入れようと京都市国際交流会館内にキッズスペースを設けたほか、子ども向けのイベントや、保育所の選び方に関するイベントなども企画している。

日本の文化を発信するのはもちろん、イベントなどを通じて、京都で生活を送る外国人の方々を支援する取り組みにも力を入れています。

現在、山本さんは広報としてそれらの情報をさまざまな媒体を活用して発信しているわけだが、課題は「必要とする人のところに、必要な情報をいかに届けるか」ということ。
例えば、近年京都市内に住むベトナム出身者の数が増えているが(韓国、中国に次ぐ3位で、2022年12月末で3,172人が在留。※数字は、京都市における外国籍の住民基本台帳登録者数)、協会として在留者の現状を把握しきれていないところがあった。

ベトナム出身の留学生がインターンに来た際に、その方といっしょに京都市内の在留するベトナムの方の現状を調べてみようと、調査活動にも取り組みました。
具体的には、日本語学校を周り、インタビュー調査などを行った結果、
- 距離的な問題があり、京都市国際交流会館内まで足を運ばない
- 主な情報源は、過去に留学していて今は現地に帰っている先輩
といった実態が見えてきた。
その結果を踏まえ、「本当にニーズのあるところに情報を届けるために、出来ることがあるんじゃないか」と考えた山本さん。

ひとまず、ベトナム語でチラシを作って、京都市国際交流会館でイベントを行いました。
単発で行ったイベントを、どう体系化していくかが今後の課題です。
国際交流に関わる仕事のやりがい・魅力

地域の方々を巻き込み、一緒に考え、実践することで、「人と人」「人と地域」「日本と外国」などをつなぎ、多文化共生を推進できるのが今の仕事の魅力と語る山本さん。

私自身、在学中の留学体験や今の職場での多国籍な人々との交流を通じて、自分の世界が大きく広がりました。
当協会でも、イベントなどを通じてそうした出会いや交流の場を数多く設けており、自分が「知らなかった世界」を知る、その橋渡しを担えるのが何よりの喜びになっています。
京都市国際交流協会では、京都市民はもちろん当地に在留するさまざまな国籍の方々を含む、多くの人との交流を通じて、「誰もが世界とつながっている」ことを実感できる社会をめざしている。
市民のみなさんや学生によるボランティア活動、外国人留学生を含むインターン受け入れなどにより人材育成にもチカラを入れ、多文化共生を身近なところから実践。その輪を少しずつ、そして着実に広げていっている。
その根底にあるのは、多文化、異文化について、地域として一緒に考え、実践していく姿勢。そこで人同士や人と地域が結びつくことで、本当の意味での多文化・異文化共生が実現される。

関心がない、知らない、ということが原因で誤解や差別といったことにつながっていくことがありますが、まずは相手のことを知り、お互いに理解し合うことが大切です。
一人ひとりの心の持ちようで世界は変わると思うので、当協会のさまざまなプログラムやイベントを通じて、小さなところから地域や人々のつながりを推進していければと思います。
関西外大での学生時代の話

ご家族が国際交流関連の団体に所属し、実家がホームステイ先のホストファミリーとして外国人の受け入れもやっていた。

私が5歳くらいの頃から毎年のように海外の方が実家に来ていたので、「目の前の人の言葉で話したい」という思いから、自然と語学学習や国際交流への関心も高まってきました。
自身も高校3年生の夏休みに、イタリアに2週間のホームステイを体験。
現地では英語ではなく、主にイタリア語でのコミュニケーションとなり、その際に「ラテン語系の言葉も魅力的で、面白いな」と感じる。
将来、語学を生かせる仕事に就きたいと考えていた山本さんは、「国際」「外国語」をキーワードに大学を探した結果、関西外大に興味を持ち、「スペイン語学科に行けば、英語はもちろん、ラテン語系のスペイン語も学べ、両方話せるようになる」のが魅力に感じ、同学科に進学する。
関西外国語大学 外国語学部 スペイン語学科に入学

在学中は、2年次の秋学期と3年次の秋学期にそれぞれ3カ月間スペインに留学をする。
その他、1年次にはインドに2週間、3年次にメキシコに2週間出かけるなど、積極的に海外に足を運んだ。
学内でも、関西外大に来ている外国人留学生と日常的に交流をしていた。

関西外大には国籍はもとより、いろいろなバックグランドをもった先生や学生がいて、交流を通じて語学力の向上はもちろん、多くの「知らないこと」に出会い、視野が大きく広がりました。

また、大学入学当初から卒業するまで、4年間京都のホテルでアルバイトを行い、朝食バイキングの会場での接客などを担当。
海外からのお客様も多く、英語やスペイン語など「その人の話す言葉」で対話したときには、すごく喜ばれたのが印象に残っているという。
就職活動はサービス・ホスピタリティ業界を中心に回り、
- ホテル
- 航空
- ブライダル
の各業界への就職をめざし、最終的に京都の老舗ホテルへ就職を果たした。
国際交流に関わる支援活動の仕事を手がけたいと、京都市国際交流協会へ

憧れの職業に就き、ホテルパーソンとして充実した日々を送った。
一期一会のおもてなしの仕事はやりがいも大きかったが、一方で、「個々の方々ともう少し長期的に接し、国際交流に関するサポートを手がけるような仕事をやってみたい」という思いも強くなっていった。
その思いを実現できる場所として転職先に選んだのが、京都市国際交流協会だった。
国や人種を飛び越えて互いの違いを認め、理解し合いながら、共生していく。
そのことを一人ひとりと一緒に考えていく場を数多くつくり、さまざまな角度から支援していく今の仕事は、まさに山本さんがやってみたいと考えていたことだった。

個々のプロジェクトなどには、こうすれば完成という明確なゴールがあるわけではなく、むしろやればやるほど「すべきこと」が広がっていきます。
ただ、前例がないからできないといった対応ではなく、課題解決に対して何ができるかを常に考え、今後もどんどんチャレンジしていければと思います。
さいごに

「やり残したことはない」と思うくらい充実した関西外大での4年間を過ごし、目標だったサービス・ホスピタリティ業界にも就職した山本さん。
自身の選んだ選択に後悔はしていないが、今から振り返って感じるのは、「もっと多くの人に会い、職業ももっといろいろな職種・業界に目を向けておけばよかった」ということだ。

在学中、いろいろなことにチャレンジできたと思っていましたが、実際に社会に出てみると、知らないことばかり…。
自分で枠を決めず、もっと多くのことに触れていたら、自分の可能性もさらに大きく広がったんじゃないかと思いました。
実際に、今の職場に来て、多国籍な人といっしょに働いていくなかで改めて実感するのが、「日本・外国関係なく、新しいことを知ると、自分のなかで世界が広がっていく」ということ。
だから、いろいろな人たちの出会いや交流が楽しいし、自分を介して人と人がつながっていくことが大きな喜びとなっている。

自分の体験からも実感をもって言えることですが、学生のみなさんには在学中からいろいろな新しいことにチャレンジしてほしいですね。
関西外大は国内外で、まさにそうした機会が数多くあるので、この環境をフルに活用して、自分の可能性を広げてください。日本の文化を発信し、世界と日本をつなぐ国際日本学科の学びにも期待しています!
\関西外国語大学公式LINEアカウント/