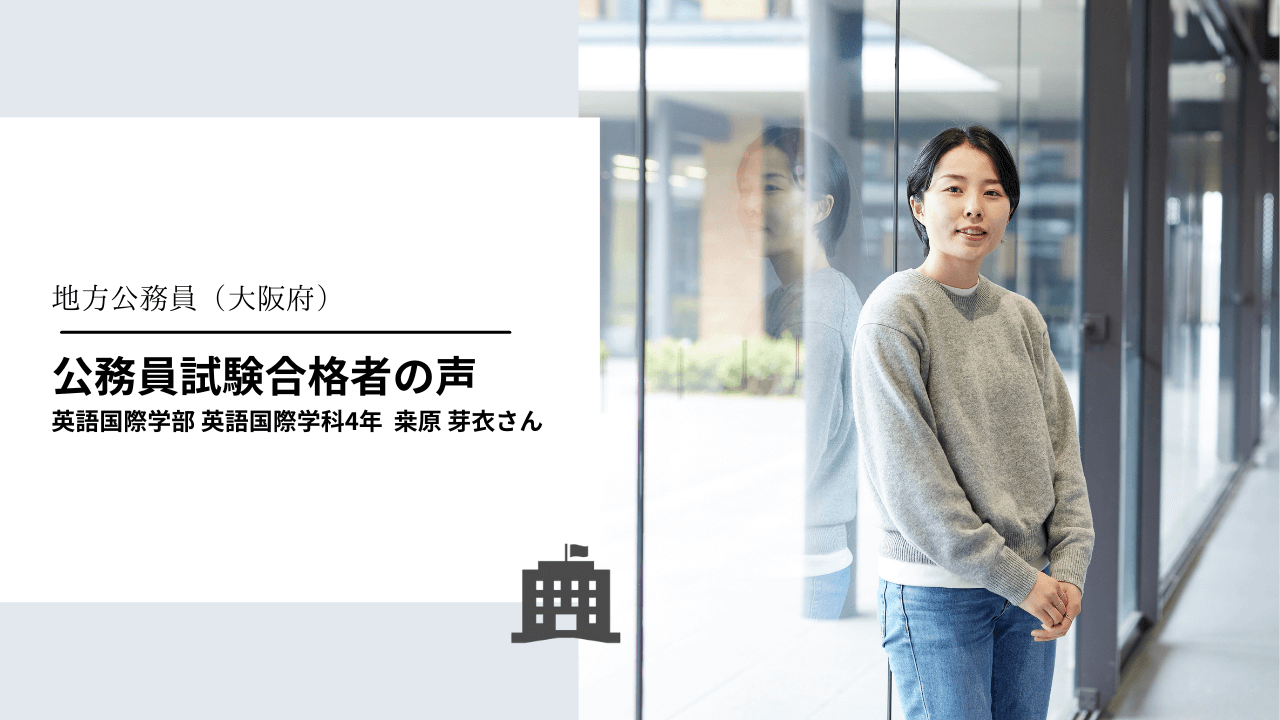こんにちは、学生広報スタッフの桒原芽衣(英語国際学部 英語国際学科4年)です!
私は24卒で公務員試験を受験し、第1志望の役所に合格することができました。
ここでは、そんな私の就活体験記を書いていこうと思います。
具体的には、
- 公務員試験対策として取り組んだこと
- 就活における「運」と「タイミング」の重要性
- 就活中の大学の授業やアルバイトとの両立について
などについて詳しくご紹介します!
学生プロフィール

- 桒原 芽衣さん
- 英語国際学部 英語国際学科4年
- 滋賀県立高島高等学校出身
- 合格先:地方公務員(地方上級、市役所)
私が公務員をめざした理由

私が就職活動について自分事として意識し始めたのは、大学2年次の3月。
まずは自分の志向を探ろうと考え、
- 一般企業
- 公務員
と大きく2つに分け、どちらに向いているかを考えました。
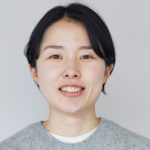
企業や業種によるとは思いますが、民間企業は専門的な分野で顧客のために働いていて、公務員は幅広い分野で利潤を目的とせずに働いているという印象でした。
さまざまな分野に携わり、広く地域の方々に貢献したいと考えていた私にとっては公務員の仕事が魅力に感じ、公務員試験にチャレンジすることをこの時点で決意しました。
公務員試験に向けた実際の就職活動

ここからは私の就職活動=公務員試験への取り組みについて書いていきます。
私が本格的に就活をスタートさせたのは3年の5月からです。
具体的には、
・学内の公務員講座を受講(面接対策、グループワーク対策など)
・SPI対策
・自治体研究
・小論文試験対策
などで、以下で個別に詳しく紹介します!
3年次から資格サポート室の公務員講座を受講
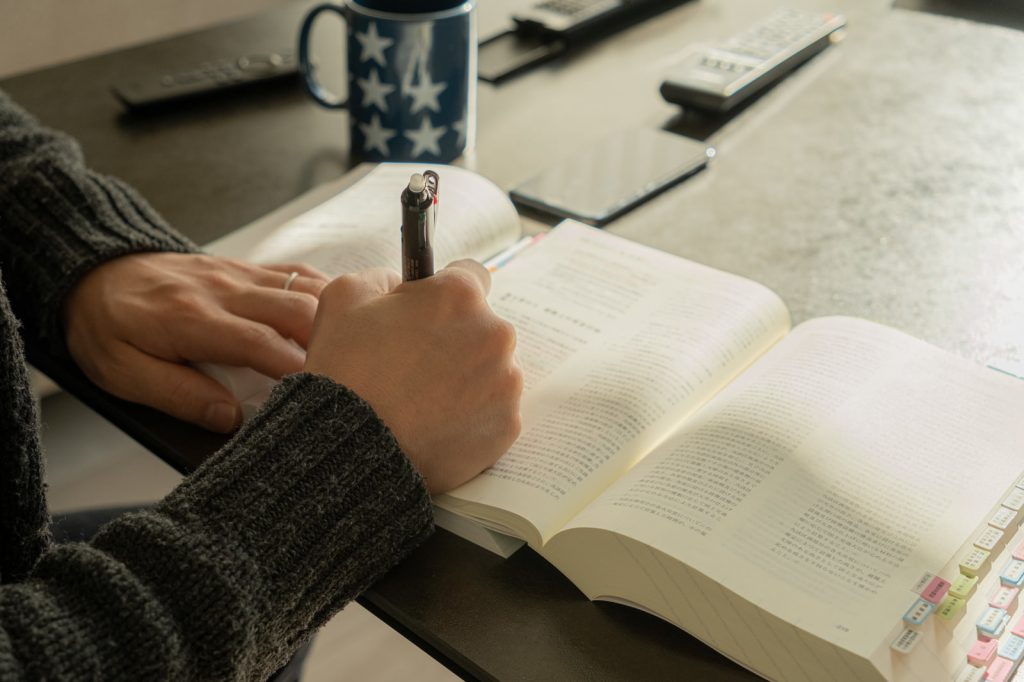
関西外大には資格サポート室があり、さまざまな対策講座を開講しています。
公務員試験対策講座としては、
- 公務員試験(入門)教養クラス
- 公務員試験(国家公務員一般職・地方上級・市役所コース)教養・専門クラス
- 公務員試験(市役所教養・警察・消防)対策講座
があり、地方公務員をめざそうと思っていた私は2つ目の「公務員試験(国家公務員一般職・地方上級・市役所コース)教養・専門クラス」を受講しました。
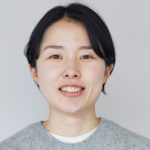
週3回、5限、6限の時間に受けていました。授業終わりに受講でき、学外の予備校に行くことを思うと移動がスムーズだったので、そのメリットは大きかったです。
有料の講座になりますが、一般的な予備校に比べてもリーズナブルな価格設定なので、その点もありがたかったですね。
講座では筆記試験対策を中心に、本番が近くなると、面接対策や小論文対策を個別にサポートいただきました。
先生方の知識が豊富なため、的確なアドバイスをもらうことができた点がよかったです。
またグループワーク対策では、学外の公務員講座を受講している人が参加する対策講座も開講され、本番は知らない人とグループワークを行うため、実践的な練習になりました。
SPI対策は問題集を繰り返し説く!
SPIとは
SPIはSynthetic Personality Inventory(総合適性検査)の略で、1974年に「学歴や職歴などの表面的な情報だけではなく、個人の資質をベースとした採用選考に寄与したい」という考え方から誕生しました。一般社会人として広く必要とされる資質(性格・能力)を測定する適性検査として利用されています。
出典:株式会社リクルート「SPIとはどんな適性検査? 多くの企業に選ばれる理由とは?」
年が明けた3年次の2月の下旬頃からSPI対策をスタート。
基本的には問題集に取り組み、間違えた問題を「✖」を付けてチェックし、「○」になるまで繰り返し解きました。
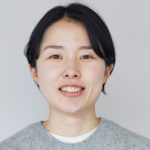
すべての問題を何周もしたわけではありませんが、苦手な問題を5~7回ほど解き、理解を深めることで解けない問題をなくすことを目標に勉強していました。
自治体研究は低年次から取り組むのがおすすめ

3月頃からES(エントリーシート)を書き始めたのですが、それまで自治体研究をしていなかったため苦戦しました。
具体的な方法としては、まずは各自治体のホームページを隈なくチェック。
携わってみたいと思った部署は自治体によって違いましたが、
- 観光課
- 環境課
- 福祉課
など、自分が興味をもった部署については特によく調べました。
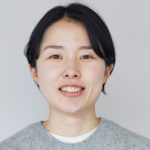
その地域の歴史や名産品、観光地、各自治体が抱えている問題などについて調べました。
対象となる項目が多かったため、時間に余裕がある時にやっておくべきだったと後悔することに。公務員をめざす方は、低年次から自治体の勉強を始めておくことをおすすめします。
小論文試験対策

小論文対策は後回しにし続け、取り組み始めたのは1つ目の小論文試験の後のこと…。
当然ながらその小論文試験はもちろんボロボロで、時間内に書き終わることができませんでした。
ここで初めて焦りを感じ、約2週間後に控えていた小論文試験に向けて、本気で取り組み始めました。
具体的には、
- 1日1つ小論文を書く → 先生(講座の先生・本学の先生)に添削してもらう
- 新聞を毎日読む(時事情報を収集)
- 小論文の参考書を読む
直前の追い込みではありましたが、2つ目の小論文試験は初回とは違い、時間内に文字数も中身の質もそれなりのものを書くことができました。
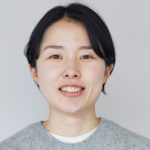
そして、無事に試験を通過することができました。当たり前のことですが、もっと早くから対策しておくべきだったと痛感しています。
就活における「運」と「タイミング」の重要性

私自身が就活を通して感じたのは、運やタイミングの重要性で、それは以下の3つのポイントからそのように感じました。
- 同じ目標を持った友人たちとの出会い
- 就職活動をサポートしてくださった先生との出会い
- 公務員試験の時期や順番
詳しく解説します。
同じ目標を持った友人たちとの出会い

志望先は違うにせよ、同じ公務員をめざす友人たちの存在が、大きな心の支えとなりました。
主に公務員対策講座の授業を通じて交流が生まれ、こうした出会いも就活を進めていく上では重要なポイントだと実感しています。
- 一緒に勉強をする(モチベーションの維持)
- 情報交換
など、公務員試験をめざすに際して、プラスになることも多かったです。
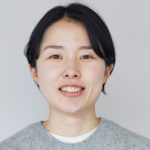
毎日朝から夜まで、友だちと大学の図書館にこもって勉強していました。大変な時期も、くじけずに乗り越えられたのは周りの友人のおかげだと強く感じています。
就職活動をサポートしてくださった先生との出会い

4年次の春学期に履修をした授業で出会った先生との出会いも大きかったです。
6月に初めて対面での面接試験があり、質問に行ったのが最初で(メディア出身の先生で、時事問題に関する質問をしにいきました)、それをきっかけに、
- 小論文の添削
- 面接
- 時事
など、さまざまな面でサポートいただきました。
先生のアドバイスで一番心に残っっているのは、「点と点で捕えるのではなく、ネットを張りなさい」という言葉。
ピンポイントで捉えようとするのではなく、ざっくりと幅広い知識を持っておくことで、面接では自分の話せる分野に持っていくことができます。
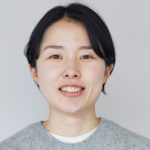
実際に本番の面接でもこの教えは非常に役立ちました。
また、第一志望の最終選考の前日の夜には、zoomにてアドバイスや激励の言葉をかけてくださり、さまざまな面から本当にお世話になりました。先生との出会いも運だったと感じます。
試験の時期や順番

民間企業は面接の日時などを相談して決めることのできるケースがほとんどだと思います。
しかし、公務員試験は試験の日時が決まっています。
そのため、〇〇市と××市の両方から1次試験の合格通知がきたとしても、2次試験の日時が被っていたらどちらかを辞退するしかありません。
そして、面接試験になると、複数日程(候補日)の中で時間も受験番号によって変わってくるので、運が悪いと試験が被ってしまうことがあります。
私の場合、幸運だったのは第1志望の自治体の試験日程が比較的遅め(後半)にあったことです。
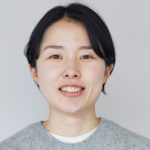
初めの頃に受けていた試験は経験値もなく、準備も整っていなかったため、不合格が続きました。この経験があったからこそ、その後の試験で合格をいただけたのだと思います。
就活中の大学の授業やアルバイトとの両立について

就活=大変、というイメージがある方が少なくないと思いますが、授業やアルバイトなどは並行して取り組めたりするのか気になりますよね。
ここでは、就活期間中の私の体験談をご紹介します。
4回生春学期の授業
卒業所要単位を取り終わっていなかったため、4科目を履修していました。
すべて週に2コマずつある科目で、就活の時期も週4回大学に通い、合計8コマ分を履修。就職試験のため何度も休んでしまいましたが、無事に全て修得することができました。
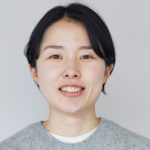
早めに必要な単位は押さえておくと気持ち的には楽になるとは思いますが、私は授業に行くことが気分転換になっていたと感じています。
なので、就活期間中に履修科目があるのは負担になるだけではなく、プラスにも働くと個人的には思いました。
就活中もアルバイト

アルバイトは週1~3回ほどしていました。
可能であれば、就活中はアルバイトをストップした方が余裕を持って就職活動に取り組めたかもしれません。しかし、アルバイトも授業と同じく、就活のことをいったん忘れ「目の前のことに集中できる」ので良い気分転換になっていたとも感じます。
就職活動や授業、アルバイトと忙しい毎日で、気合い一本で乗り切っていました。
その分、自分自身の受験番号を見つけた時の達成感や喜びは感じたことがないほどに大きなものでした。
さいごに

この記事では、私の就活体験について書いていきました。
あらためて振り返ってみると、準備不足で、失敗や後悔することが少なくなかったように感じます。
1年前の自分にアドバイスができるのであれば、後回しにせず、早めに対策すること、このことを声を大にして伝えたいです。
また、公務員試験の結果が出るのは一般企業などより比較的遅いので、周りが内定をもらっている声を聞くたびに焦りを感じました。
しかし、比べても落ち込むだけだと気づき、考えることを意識的にやめると、気持ちも少し前向きになることができました。
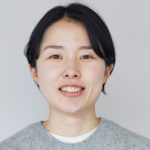
何よりも、絶対に公務員になりたい!という強い気持ちがあったため、折れずにがんばれたのだと思います。
この記事が、就職活動を控えている方や、活動中の方に少しでも役立てばうれしいです。皆さんのご健闘をお祈りします!