大学院 外国語学研究科
GRADUATE SCHOOL
FOREIGN STUDIES RESEARCH DIVISION
「英語学」と「言語文化」2つの専攻で
国際社会に貢献する高度専門職業人を育成

博士前期課程 2年制 英語学と言語文化の“2専攻・5つの分野”
博士前期課程では、グローバル化が進む時代と社会の変化に対応すべく、2024年にカリキュラムを刷新しました。英語学と言語文化の2つの専攻のもと、専門知識の学修(コースワーク)から研究活動(リサーチワーク)へ有機的につながる教育課程を構築しています。英語学専攻には英語学と英語教育の2分野、言語文化専攻にはイベロアメリカ文化、日本語学・日本語教育、国際共生コミュニケーションの3分野で、高度な言語コミュニケーション能力を基盤とした、現代の国際社会に貢献する豊かな教養を備えた人材の育成に取り組んでいます。
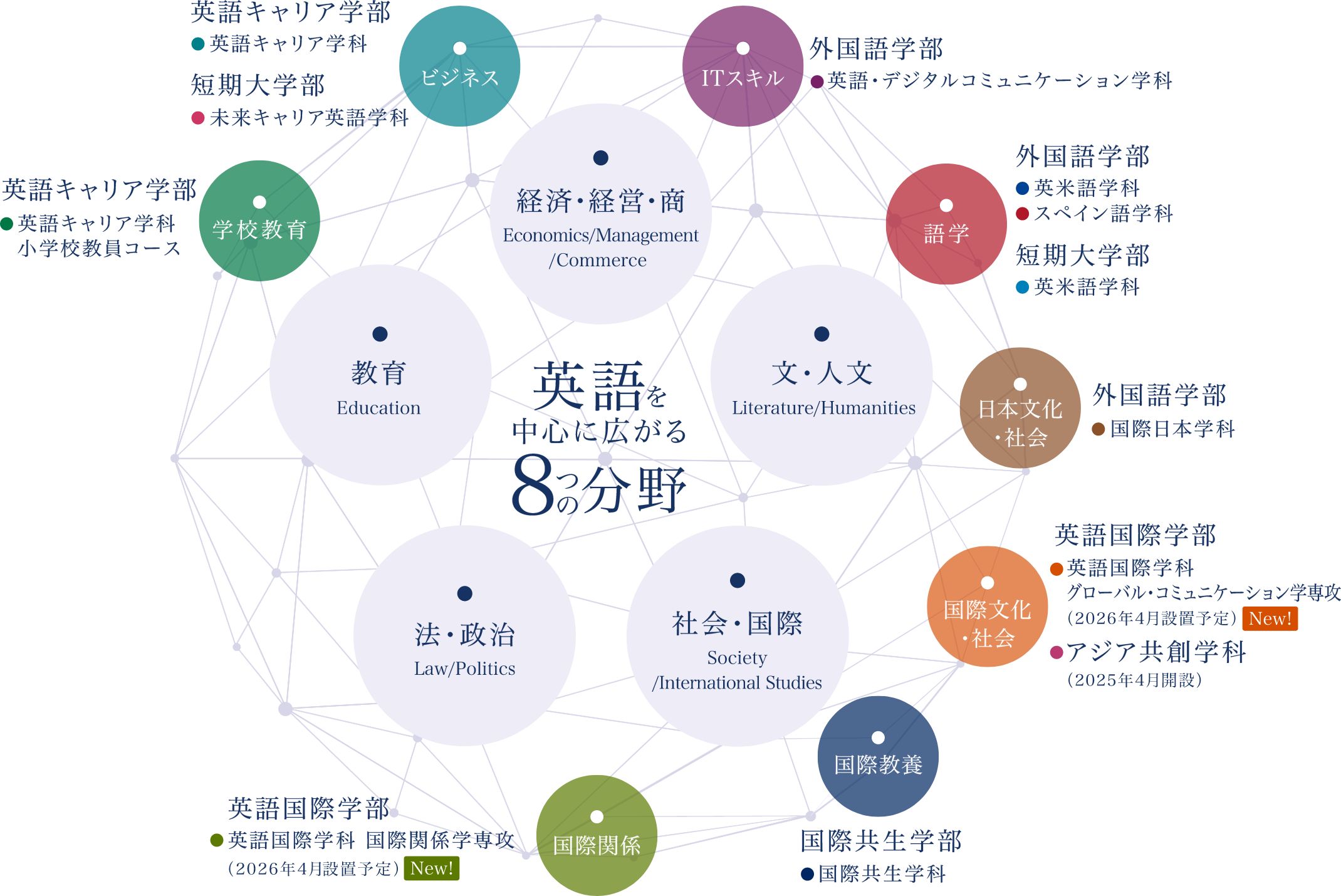
01 英語学専攻
英語学
言語学の理論や分析法を学び英語学研究を進め、英語の使い方・仕組みに関する知識を深めます。この分野で獲得した英語運用能力、専門知識・研究能力、教養、国際性、実践力に基づき、言語の観点からグローカル化(Globalization+Localization)する現代社会の要請に応えうる人材をめざします。
担当教員からのメッセージ

言語データも使ってみましょう
近年、コンピュータによる自然言語処理技術の発展は目覚ましく、例えば、自動翻訳では100言語以上を対象に、瞬時に、それも、かなり適切に翻訳できるようになりました。一説によれば、その翻訳能力はTOEICスコアに換算すると900点を超えるとも言われています。こうした技術の開発には言語データ(コーパス)が欠かせません。コーパスは言語学においても用いられています。例えば、新聞やインターネットの英語を集積したコーパスを用いると英語の慣習的用法が、また、乳幼児や第二言語学習者の英語運用を対象とするコーパスを用いると英語の習得過程がそれぞれ調査できます。こうしたコーパスに基づく調査を行うには、まず、英語の言語特性、例えば、言語機能・認知能力などの基本原理、言語のさまざまな用法、そして言語を取り巻く文化・社会を理解する必要があります。皆さんと一緒に英語の言語特性をコーパスに基づき研究できることを楽しみにしています。
小谷 克則 教授
英語教育
現在のグローバル社会においては、確かな英語力を身に付けた人材の養成が強く求められています。英語という国際語を使いこなし、自分の気持ちや考えを表現し、人と交渉できる能力は今後ますます求められていくでしょう。この分野ではこうしたニーズに対応できる指導者を養成します。
担当教員からのメッセージ

人はどのような理解に基づいて言葉を使っているのか
私は英語の文法について、コーパスのデータを利用したり、インフォーマントに情報提供してもらいながら、調査をしています。人はなぜ言葉を自由に操ることができるのでしょう。これは言語学にとってとても大きな問題であり、さまざまな意見が提出されていますが、今だに満足のいく答えは出ていないと思います。私にもまだ答えはないのですが、それでも、言葉は人が使ってメッセージ内容を相手に伝えるためにあるものですから、少なくとも、人の世界の見方、事態の捉え方を直接反映するものであるはずだと思います。
メッセージ内容が異なれば、自ずとそれは表現形式の違いとなって現れるでしょうし、表現形式が異なるなら、その背後に込められた意味内容にも何らかの違いが存在するはずだと思うのです。
『形が違えば意味も違う』という、古来から存在する(とても古くさいかもしれませんが)考え方を基本として、言葉の実態の有り様を観察、研究していくことは、英語という外国語を教えていく場面でもきっと役に立つものと思います。
英語の表現に込められた意味や形式の違いがもたらす効果について、なぜそうなっているのかを考えることは、文法学習や英語教育にとって重要な知見を与えてくれるものだと思うのです。そのような視点に立って、みなさんと言葉を観察していくことができれば、と思っています。
岡田 禎之 教授
取得可能な学位ごとの3つのポリシー
02 言語文化専攻
イベロアメリカ文化
スペイン・ラテンアメリカの文学やその他の文化を研究する「イベロアメリカ文学・文化」、地域全体、もしくは各国における歴史、社会、政治・経済を対象とする「イベロアメリカ地域研究」、スペイン語は単一ではなく、地域変異が存在するということを理解しつつ、言語学の側面からスペイン語を通時的・共時的に研究する「スペイン語学」の3つの分野があり、広大なイベロアメリカ地域を探求します。
担当教員からのメッセージ

言語変化を体系的な変遷で捉える
専門はスペイン語学です。主に時制・法形式を対象としてその動向を研究しています。最近では現代スペイン語が多いですが、古い時代も研究対象としています。
研究の一つの例ですが、皆さんは接続法過去には2種類あることを学びましたよね。-ra形と-se形です。この2形式が用法上どう違うのか、その使用地域は、といった研究は現代スペイン語の問題です。しかし、どうして同じ意味機能になったのか、という問題を探求するためには古いスペイン語を意味的・統計的に調べなくてはなりません。ただ、同形式だけを追っていては擬似相関に陥ってしまう可能性があります。「アイスクリームが売れるほど水難事故が増える」という統計自体は真実なので、それを近視眼的に見てしまうと、アイスクリームが水難事故の「犯人」であるという誤った因果関係を導いてしまいます。すなわち、上記2形式に関する真の原因を突き止めるためには、当該の形式だけでなく、それらを取り巻くさまざまな要素(-ra形の元の機能である直説法過去完了の機能を担うことになる“había+p.p.”の動向、“haber+p.p.”自体の形態統語的変化、本動詞haberとtenerの意味の変遷、など)を体系的な変遷として観察する必要があります。緻密で地道な作業ですが、「原因はアイスではなく気温だ」ということがわかったときには至極の達成感が味わえますよ。
辻井 宗明 教授

全体知をもとめて
流行とは関わりなく、だれにでも、毎日見ても飽きない、何か惹かれる、理屈なしに好きな絵画の1枚くらいはあるのではないでしょうか。その絵画との出会いは、おそらく偶然にすぎません。研究も最初は素朴な感情からスタートします。どうなっているのか、なぜこうなるのかと、あるいはこうなるのではないかと、長年、問い続けた集積が研究を形づくります。その原動力は研究対象に対する好奇心と探究心に他なりません。メキシコ植民地期の先住民を研究テーマにしています。私が理解した欠片を丹念に組み合わせ続けたあとに、これまでとは異なる彼らの全体像を描き、植民地社会の全体知へとつながればと願っています。段階を追うごとに見えてくる景色が微妙に変化するのも研究の醍醐味です。今、自分なりに深く知りたい、育てていきたいと考えている興味や関心があるなら、学び続けてほしいです。
林 美智代 教授
日本語学・日本語教育
言語が重要な役割を果たす国際化・国際交流の時代にあって、その一翼を担う日本語に対する関心も年々高まっています。日本語学習を支援する日本語教育の重要性が高まり、その基盤となる日本語研究(日本語学)もその推進が求められています。この分野では、互いに密接な関係にある日本語学と日本語教育を両輪として、時代の要請に応えていくことをめざします。
担当教員からのメッセージ

「日本語学」という研究への慫慂(しょうよう)
「日本語学」の研究と聞くと、何か難しいイメージを抱きませんか。しかしながら、研究対象は、文献だけでなく、現代の日本語文法、敬語、若者言葉、メール言語などもあり、普段用いている母語を内省化する学問といえます。勿論、先行研究を踏まえ、オリジナリティを有する論文を執筆するためには、日々の研究に対する自己研鑽が必要になります。外国人留学生にとって、他言語の日本語を研究することは、さらに難解なことと感じるかもしれません。しかし、心配は無用です。院生一人に主、副指導の教員が、きめ細かな研究の支援をします。これまで不明であった日本語の理論を解明できたときは、言い尽くせない喜びを感じるはずです。私自身は、現在の研究テーマの「社会言語学」「日本の言語学史」に深く魅了されたのは、大学院博士後期課程在学中でした。一つの研究テーマを突き詰め、学問を究めることは、自己の精神の涵養につながります。ぜひ、本学大学院で、学問の楽しさを共有しましょう。
柿木 重宜 教授
国際共生コミュニケーション
情報通信技術の進展により、人、モノ、情報の国際間移動は活発化を増し、各国の相互依存性は高まっています。しかし、ボーダーレス化の進行にも関わらず、国際紛争、格差拡大、地球温暖化等、国際間の問題は増加の一途をたどっています。この分野では、国際社会で活躍するグローバルな人材を育成し、コース修了後にさまざまな活動を通じて国際社会の発展に貢献することを目標にしています。
担当教員からのメッセージ

世界動向の分析手法を身に付けて国際社会で活躍しよう
現在、ウクライナ情勢を含めて世界は激動の時期を迎えており、今後どのように推移するのか目が離せません。このような錯綜した国際社会で働くためには、異なる国の文化・社会の理解を通じて多様な価値観を尊重するという視点が不可欠です。そのためには、まず自国の文化・社会を知り、他国との類似点、相違点を客観的に把握することが肝要です。
このコースでは、そのために必要な講義がすべて英語で用意されており、国際的な視野を広げることが可能となります。しかも先生との距離が近いので、活発な質疑応答を通じて満足度が高い講義を受けることができます。また、国際社会で働くためには不可欠な自らの意見を英語で説得的に伝えるスキルも身に付けることができます。私の専門分野は日本経済論です。日本経済はこれまで東日本大震災、新型コロナウイルスの感染拡大など多くのリスクに直面し、停滞を続けてきました。なぜ日本経済は長期停滞を続けているのか、データを用いて客観的な分析をすることが私にとっての研究テーマです。本コースには、日本経済以外にも世界の政治経済分析や途上国の経済発展を専門とした教授陣が揃っています。複雑な世界動向の分析に関心があり、国際社会で活躍したい皆さん、ぜひこのコースで一緒に学びましょう。
小川 一夫 教授

戦争と平和の問題を理論的に分析する
現代の国際関係は政治・経済・社会・文化・宗教・テクノロジーなどが複雑に絡み合ったものです。今世紀における国を超えてのヒト、モノ、カネの流れは劇的に増加し、ボーダーレス・ワールドと言われて久しくなります。しかし、国家間の国境が本当に無くなった訳ではなく、むしろそれらを巡っての争いは未だ絶えません。ロシア=ウクライナ戦争やイスラエル=ハマス紛争を見れば一目瞭然です。そして世界を脅かす核兵器の全廃は未だ程通い状況です。さらに中国のアメリカ覇権への挑戦は誰の目にも明らかになっています。私は国際政治学者として、日米同盟やインド太平洋地域の安全保障問題に取り組んできました。今後衰退傾向が顕著になると考えられるアメリカの今後の動向と、それに対して勃興する中国との間にいる日本の立場は、とてつもなく重要と考えます。
一見混沌とした政治現象も理論を使うことで、理解を大きく進めることができます。それは複雑に絡み合った糸を解したり、切ったり、繋げたりすることにも喩えられます。この大学院で、国際関係のダイナミズムを研究し、現代の国際政治上の問題を分析できるような人材をめざしませんか。
酒井 英一 教授
取得可能な学位ごとの3つのポリシー
博士後期課程 3年制 外国語大学初の“ドクターコース”
1979年、全国の国公私立外国語大学のトップを切って、外国語大学初の“ドクターコース”が本学で誕生しました。2024年3月まで、85人に博士号の学位を授与してきましたが、彼らは世界にはばたき、教員や研究者として活躍しています。博士後期課程では、今日のグローバル化社会において、教育を担う者としての自覚や意識の滋養、また学生に対する教育を施すための確かな能力と、自立して研究活動を行うことができる能力を兼ね備えた大学教員をはじめとする教育者などとして活躍できる優れた人材の育成に主眼を置きます。英語学専攻では、英語学、英語教育の研究領域に関して、言語文化専攻では、スペイン語学、日本語学の研究領域に関わり、それぞれ高度な知識の修得、および自立して研究活動を行える学究的能力の養成をめざします。

01 英語学専攻
高度な英語運用能力を持ち、英語学や英語教育学の分野で自立して研究する能力と、今日のグローバル社会で活躍できる人材を育成する教育能力を兼ね備えた大学教員等の高度専門職業人育成が目的です。
担当教員からのメッセージ

英語語法文法から生成文法理論へ
言語は人間の精神のありようを映し出す鏡です。その言語は形(音韻・統語)と意味の組み合わせでできています。私は言語のうちの現代英語に限って研究していますが、現代英語の研究を通して人間性をも探究したいと思っています。そのために、自然言語の生得的・遺伝的基盤である普遍文法を前提とした生成文法理論の立場をとっています。最近では、現代英語の大規模電子コーパスを利用して、英語の構文における基本形と変種を中心に、補部と付加詞、構文イディオム、意味と形のミスマッチ、核から周辺への動的な展開の法則等に関する研究に取り組んでいます。指導方針は、生成文法の思考法を深く理解したうえで、生の言語資料をもとに細かな言語事実をも観察でき(英語語法文法家としての能力)、記述でき(記述文法家としての能力)そして説明できる能力(生成文法家としての能力)を養成することです。
大室 剛志教授
取得可能な学位ごとの3つのポリシー
02 言語文化専攻
イベロアメリカ文化
言葉のメカニズムを特徴付ける重要な研究分野である意味論と語用論の基本的な研究方法と日本語および中国語教育、そして外国語教育への応用の可能性を考察。言語データの収集と分析、言語事実からの仮説構築、論文と引用文献リストの作成、学会での研究発表と議論の方法など、総合的に指導と助言を行います。
担当教員からのメッセージ

言語・文化の比較対照研究
言語と文化は独立した体系として成り立ち、相互関係を持ち、作用し制約し合っています。
イヌイットが「雪」を表す単語は7つあり、それぞれが異なる状態の雪を表現します。アラビア語には「駱駝」を表す数百の単語があり、駱駝の年齢・性別・種類・大小を区別しています。日本語には「雨」を表現する言葉が少なくとも39語あり、季節・時期・雨の強さ・雨量・降雨時間の違いを表します。また、中国語に親族関係を表す言葉が数多く存在するのは、家族関係を重要視する伝統文化からです。
本研究の目的は、日中英言語文化の比較対照を行い、異文化交流の場で容易に起こりうる誤解や摩擦を考察し、コミュニケーション力を高め、的確な言語表現を身に付けることにあります。言語・文化の比較対照研究に高い志を持つ学生が本学の博士前期・後期課程で学ぶことを期待します。
靳 衛衛教授
