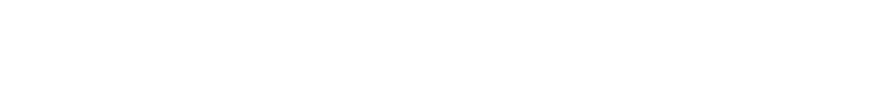世界中の人と心を通わせる「言葉」を学ぼう。
まだ知らない「文化」を感じよう。
あなたの可能性を広げるキャンパスで
新しい価値観に触れてみよう。
みずから一歩を踏み出す勇気。
言語や文化の壁を越えた先にある気づき。
その先に待っているのは、どんなあなたでしょうか。
本当の挑戦は、ここから。
“語学の、その先”を見つけよう。 Take Action!
-
卒業後の活躍

急成長するアジアと正面から向き合いながら、海外営業としてのスキルを伸ばしている
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 新たな価値を創る -
教授からのアドバイス

多様性時代を生き抜く力を養う、理想の環境がここにはある。
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 多様な価値観と向き合う -
教授からのアドバイス

多様性に触れながら、興味を持ったことに心を尽くしていく。そうすれば、道は拓かれる。
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う -
教授からのアドバイス

国際金融の経験をもとに語る。これからの時代で通用するグローバル社会を生きるヒントとは
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
卒業後の活躍

ニューヨークに留学したからこそ気づいた自分にしかない強みを生かして働くということ。海外で働きたいという思いから外大に。
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 新たな価値を創る -
卒業後の活躍

留学で身に付けた学びと行動力で、私は客室乗務員として世界を飛んでいる
■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する■ 新たな価値を創る -
卒業後の活躍

留学中に踏み出した一歩が国際物流という仕事で生きている
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う -
卒業後の活躍

英語でビジネスを学んだからこそ外資系企業のマーケティングを楽しんでいる
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 諦めず最後までやり切る -
卒業後の活躍

留学生たちとの出会いと交流がメルカリという職場で息づいている
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す -
卒業後の活躍

客室乗務員からキャリアコーチへ。関西外大で学んだのは、自分で人生を切り拓く力。
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 新たな価値を創る -
学内での学び

留学経験で知った日本の素晴らしさをこれからは私が世界に伝えていく
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
外大生の入学理由

中学校の先生になる。関西外大の短大進学を決めて良かった
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 仲間と共に乗り越える -
外大生の入学理由

日本の最初の印象を決める存在、グランドスタッフが夢から目標になった
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 仲間と共に乗り越える -
学内での学び

国際交流イベントや留学先で交わした言葉の一つひとつが私の心を広げてくれた
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
学内での学び

スペイン留学で出会った、言葉と文化とたくさんの友人
■ 夢や目標を持つ■ 計画性を持って行動する■ 多様な価値観と向き合う -
学内での学び

英語を楽しく教えられる先生に!そんな夢を実現するために挑戦し続けている
■ 何でも挑戦してみる■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
学内での学び

留学という経験があったからこそ、国際問題に関心を持つことができた
■ 計画性を持って行動する■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

言語の壁にぶつかった悔しさを糧に、人と人との架け橋になる。
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

多文化が交わる関西外大。アートには、国境を越えて心をつなぐ力がある。
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

国際交流も、ボランティアも、一生懸命に挑戦できる機会はいくらでもある。
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 新たな価値を創る -
キャンパスライフ
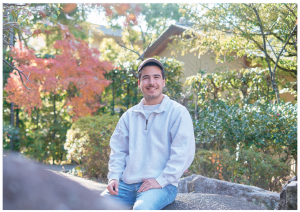
留学経験は人生の財産。実践的な日本語や新鮮な日本文化を仲間と学ぶ
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
キャンパスライフ

「結」での暮らしが、日本への好奇心を加速させる。
■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

未来の外大生への貢献が、新しい自分に出会うきっかけをくれた。
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 他者に貢献する -
キャンパスライフ

さまざまな価値観にふれながら、教員の夢をまっすぐに追いかける
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 計画性を持って行動する -
キャンパスライフ

感謝の意義は世界共通。日本拳法で学んだ精神を母国へ。
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
キャンパスライフ

「結」での生活や留学、交流イベント。そのすべてが、自分を変えてくれた
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

憧れのハリウッド俳優へ。4年間で得た自信が、背中を押してくれる
■ 自らチャンスを作り出す■ 仲間と共に乗り越える■ 諦めず最後までやり切る -
外大生の入学理由

関西外大の学びと「結」の仲間たちが、客室乗務員の価値観を教えてくれた
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 多様な価値観と向き合う -
外大生の入学理由

専門留学で身に付けた学びで世界にスポーツの喜びを伝えていく
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
外大生の入学理由

客室乗務員になるためにセカンドステージで人間力を磨き、自分を成長させる
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 他者に貢献する -
キャンパスライフ

テネシー州からやってきた私に日本の文化がゆっくり染みこんできた
■ 世界への好奇心を持つ■ 計画性を持って行動する■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

フィンランドから日本に来て一生の友だちができたことが嬉しい
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 仲間と共に乗り越える -
キャンパスライフ

関西外大に来たことで、日本とメキシコの芸術のつながりを知った
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う -
キャンパスライフ

アメリカから日本への留学。より自覚を持てた自分自身の存在意義
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 新たな価値を創る -
キャンパスライフ

異国の地でワクワクすることが私のなかで毎日起こっている
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
卒業後の活躍

「結」で身に付けたコミュニケーション能力がコンサルタントとしての力になっている
■ 夢や目標を持つ■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる -
卒業後の活躍

関西外大での学びが、AIの時代にも負けない力を授けてくれた
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
卒業後の活躍

世界中の人が集うホテルで私が学んできたホスピタリティを発揮する
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 新たな価値を創る -
教授からのアドバイス
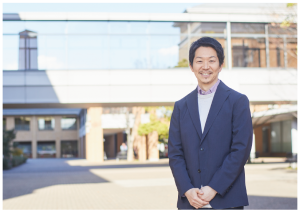
国際的なキャリアをめざすために、10代から取り組みたい意識改革とは
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
学内での学び

海外留学の準備を日本のキャンパスで「Super IES プログラム」がめざすもの。
■ 夢や目標を持つ■ 計画性を持って行動する■ 仲間と共に乗り越える -
学内での学び

変化の速いデジタル時代を生きるあなたへ。国際社会で求められる人になるためのヒント
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
教授からのアドバイス

より良い世界をつくりたいあなたへ。グローバルに活躍するために必要な力とは
■ 世界への好奇心を持つ■ 計画性を持って行動する■ 多様な価値観と向き合う -
留学

国際ビジネスを学びに、憧れのオランダへ!人として成長し日本と世界の架け橋をめざす
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
卒業後の活躍

海外留学で学んだホスピタリティフィンランドの空を舞台に異文化をつなぐ接客を極める
■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える■ 他者に貢献する -
卒業後の活躍

オランダ留学で磨いた国際ビジネスの知識を武器にヨーロッパ各国との貿易の最前線に立つ
■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す -
留学

観光大国スペインで学んだツーリズム。留学を通して、将来の夢が見つかった
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
留学

世界が認めるハイレベルなホスピタリティ教育。フィンランドで知識と国際感覚を磨き、夢へ大きく前進!
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 新たな価値を創る -
学内での学び

英語×デジタルの“二刀流”グローバル社会から必要とされる人材になろう。
■ 世界への好奇心を持つ■ 計画性を持って行動する■ 多様な価値観と向き合う -
学内での学び

入学直後からオールイングリッシュ。半年後の成長度合いは?
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 仲間と共に乗り越える -
卒業後の活躍
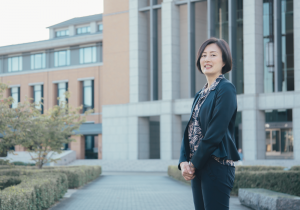
日本のお客様に「本物のハワイ」を伝えたい外大のグローバル環境が旅行好きの原点
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 他者に貢献する -
教授からのアドバイス

世界的プレゼンターに学ぶ、国際社会で自分を表現する方法。
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 新たな価値を創る -
卒業後の活躍

日本のために働くやりがい、外交官に必要な資質と力は関西外大で身に付けられる
■ 夢や目標を持つ■ 計画性を持って行動する■ 他者に貢献する -
教授からのアドバイス

「ホスピタリティ」の発揮によって幸せな人生を!ホスピタリティ=心×感知力×表現する力
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
キャンパスライフ

真剣だからワクワクできる。高校生向けイベント「FIND」の舞台裏。
■ 夢や目標を持つ■ 仲間と共に乗り越える■ 新たな価値を創る -
卒業後の活躍

現地留学で修得したスペイン語を生かしサービスのプロをめざす。
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 他者に貢献する -
卒業後の活躍

社会のすべては「人」が基本アメリカ留学で学んだ心理学を生かしてグローバルな組織改革に挑む。
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 諦めず最後までやり切る -
留学

留学で心に誓ったNow or Neverの精神が今も自分を支えている。
■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す -
学内での学び

4年間で学んだのは、積極的に行動すれば現実を変えられること。
■ 世界への好奇心を持つ■ 計画性を持って行動する■ 自らチャンスを作り出す -
学内での学び

言語を学んだことで出会いが生まれ、視野が大きく広がった。
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
外大生の入学理由

子どもの心に寄り添い、英語を学ぶ楽しさを伝えられる教員に。
■ 夢や目標を持つ■ 仲間と共に乗り越える■ 他者に貢献する -
留学

挑戦の4年間、さらにレベルアップした自分に出会えた。
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 他者に貢献する -
学内での学び

課題解決型授業で学んだ調節する大変さ、大切にしたいのは信頼関係を築くこと。
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
外大生の入学理由

ジェンダー平等の先進国オランダで周囲と対等に意見交換。
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 諦めず最後までやり切る -
外大生の入学理由

CAになりたかった私が留学後、「会計学」に夢中なった理由とは?
■ 夢や目標を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
留学

教育の力で未来の子どもたちの可能性を広げたい。アメリカの大学院進学はその一歩。
■ 計画性を持って行動する■ 自らチャンスを作り出す■ 諦めず最後までやり切る -
外大生の入学理由

留学で大きく変わった進路。アメリカでの経験が、未来を切り開いた。
■ 夢や目標を持つ■ 計画性を持って行動する■ 自らチャンスを作り出す -
留学

グローバルビジネスの面白さをオランダの授業で体感。
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
留学
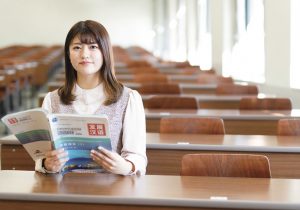
成長が進む中国経済について学び中国の大学院進学を決意
■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 多様な価値観と向き合う -
留学

2つの国で議論や交流を深め、以前と違う私になれた。
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 諦めず最後までやり切る -
外大生の入学理由

とことんスペイン語と向き合いさまざまな価値観に触れ成長できた。
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 諦めず最後までやり切る -
学内での学び

私の外大ストーリー【外国語学部英米語学科】
■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 計画性を持って行動する -
外大生の入学理由

私の外大ストーリー【英語キャリア学科小学校教員コース編】
■ 夢や目標を持つ■ 仲間と共に乗り越える■ 他者に貢献する -
外大生の入学理由

私の外大ストーリー【短期大学部編】
■ 夢や目標を持つ■ 計画性を持って行動する■ 自らチャンスを作り出す -
外大生の入学理由

私の外大ストーリー【Global Experience編】
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 新たな価値を創る -
学内での学び

私の外大ストーリー【外国語学部スペイン語学科編】
■ 世界への好奇心を持つ■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
教授からのアドバイス

留学を目指すあなたへ。文化や考えの違う人同士が分かり合うために大切なこととは。
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
卒業後の活躍

世界を舞台に働く力は、多文化なオーストラリアへの留学で培った。
■ 多様な価値観と向き合う■ 諦めず最後までやり切る■ 他者に貢献する -
教授からのアドバイス

夢がなかなか見つからなくて立ち止まっているあなたへ。自分らしく生きるためのヒント。
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う -
学内での学び

私の外大ストーリー 【英語キャリア学部編】
■ 世界への好奇心を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
卒業後の活躍

「語学+α」その専門性をオランダで磨いたからいまがある。
■ 自らチャンスを作り出す■ 多様な価値観と向き合う■ 諦めず最後までやり切る -
卒業後の活躍

ブランドの価値を高めるために、次は何を仕掛けようか
■ 何でも挑戦してみる■ 多様な価値観と向き合う■ 他者に貢献する -
卒業後の活躍

報道の現場は、思いを伝える力を育んだニューヨーク。
■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す■ 諦めず最後までやり切る -
学内での学び

2年後にはじまる、新しい自分。関西外短で見つけた、夢。
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 計画性を持って行動する -
キャンパスライフ

4年間、オールイングリッシュ。世界レベルで留学生と学ぶ「国際共生学部」とは。
■ 世界への好奇心を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 自らチャンスを作り出す -
キャンパスライフ

留学の「質」を高めるために開発されたSuper IESプログラムとは?【学生編】
■ 夢や目標を持つ■ 仲間と共に乗り越える■ 諦めず最後までやり切る -
キャンパスライフ

英語で学ぶ留学のために開発されたSuper IESプログラムとは?【先生編】
■ 夢や目標を持つ■ 多様な価値観と向き合う■ 仲間と共に乗り越える -
卒業後の活躍

服を作る女性と、服を着る女性。どちらの暮らしも豊かにしたい。
■ 夢や目標を持つ■ 何でも挑戦してみる■ 新たな価値を創る -
留学

2年半で2つの学位。短期大学部ダブル・ディグリー留学とは。
 留学
留学
 学内での学び
学内での学び
 外大生の入学理由
外大生の入学理由
 キャンパスライフ
キャンパスライフ
 卒業後の活躍
卒業後の活躍
 教授からのアドバイス
教授からのアドバイス